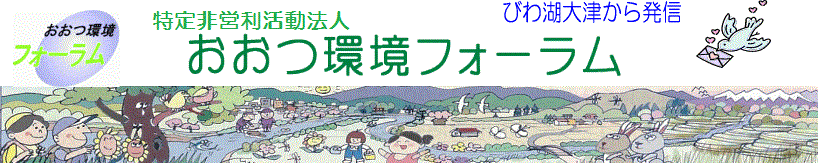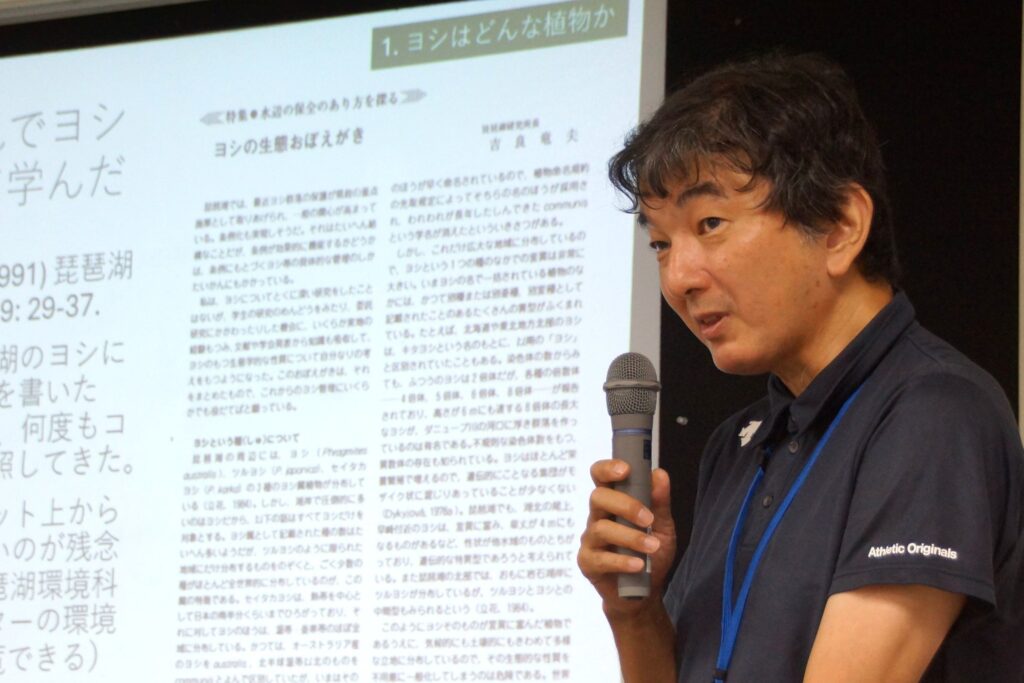令和7年9月27日(土)、おおつ市民環境塾2025講座6「ヨシ原の変遷と生物多様性」を開催いたしました。
今回の講座の講師はお二人です。
琵琶湖博物館の総括学芸員の大塚泰介氏

滋賀県琵琶湖環境部 主任主事の土田真由氏

まずは、土田講師から、滋賀県のヨシ原保全についてお話がありました。
ヨシ群落は、魚類・鳥類の生息など、豊かな生物相をはぐくみ、琵琶湖の環境保全に大きな役割を果たしています。
また、古来より、屋根やすだれなどとして利用する等、人とのかかわりが深いものでもありました。
滋賀県では、ヨシ群落を保全するために、行政・地域・事業者とボランティアが連携し、「守る」「育てる」「活用する」という多面的な取り組みがなされているとのことです。
次に大塚講師より、
・ヨシはどんな植物か
・ヨシ帯の生物
・ヨシ帯の水質浄化機能
・琵琶湖のヨシ帯の破壊と再生
・より良い保全と再生
という各テーマについて丁寧な説明がなされました。
琵琶湖のヨシ帯は1980年代を中心に、琵琶湖総合開発による湖岸底建設で破壊されました。
しかし、市民から批判の声が上がり、またヨシ帯の多面的な機能が明らかになると、水資源開発公団や県も保全・再生へと舵を切りました。
ヨシ帯の再生には困難もありましたが、1990年代後半に再生のための技術が確立され、ヨシ帯の面積は急激に回復したとのことです。
ヨシ帯には、生物多様性の保全、水質浄化、半栽培の場、環境学習と交流の場など、多くの機能があります。
現在も行政と市民(プラス企業)が協力して、ヨシ帯環境の改善が進められています。

参加された方から、ヨシの多様な側面を知ることが出来て、とても勉強になったと感想をいただきました。